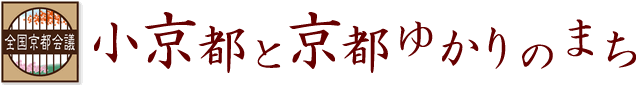足利 あしかが
中世の歴史薫るまち足利 ~祈り・願いの叶うまち~
 足利は室町幕府の将軍家、足利氏発祥の地として知られています。石畳みのある街並みには、源姓足利氏の学問所として創建説のある日本遺産「史跡足利学校」、本堂が国宝に指定された足利一門の氏寺「鑁阿寺」があります。また、伊萬里・鍋島の世界的コレクションを所蔵する「栗田美術館」や600畳敷の大藤棚やイルミネーションが有名な「あしかがフラワーパーク」は多くのお客様で賑わいます。清流渡良瀬川や、緑豊かな山並みなど豊かな自然に恵まれ、歴史と伝統に彩られた「東の小京都」と称される美しい街です。
足利は室町幕府の将軍家、足利氏発祥の地として知られています。石畳みのある街並みには、源姓足利氏の学問所として創建説のある日本遺産「史跡足利学校」、本堂が国宝に指定された足利一門の氏寺「鑁阿寺」があります。また、伊萬里・鍋島の世界的コレクションを所蔵する「栗田美術館」や600畳敷の大藤棚やイルミネーションが有名な「あしかがフラワーパーク」は多くのお客様で賑わいます。清流渡良瀬川や、緑豊かな山並みなど豊かな自然に恵まれ、歴史と伝統に彩られた「東の小京都」と称される美しい街です。
足利の見どころ
史跡足利学校
 足利学校は、日本で最も古い学校として知られ、その遺跡は大正10年に国の史跡に指定されています。
足利学校は、日本で最も古い学校として知られ、その遺跡は大正10年に国の史跡に指定されています。
足利学校の創建については諸説ありますが、室町時代に関東管領・上杉憲実(うえすぎのりざね)が、学校を再興してからは、学問の灯を絶やすことなくともし続け、学徒三千といわれるほどに隆盛しました。1549年にイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルにより「日本国中最も大にして、最も有名な坂東の大学」と世界に紹介されました。
鑁阿寺(ばんなじ)
 源姓足利氏2代目義兼が1196年、邸内に持仏堂を建て、守り本尊として大日如来を祭ったのが始まりで、3代目義氏が堂塔伽藍(がらん)を建立し足利一門の氏寺としました。
源姓足利氏2代目義兼が1196年、邸内に持仏堂を建て、守り本尊として大日如来を祭ったのが始まりで、3代目義氏が堂塔伽藍(がらん)を建立し足利一門の氏寺としました。
周囲に土塁と堀をめぐらした寺域はほぼ正方形で、鎌倉時代の武家屋敷の面影を今に伝えています。大正11年3月、「足利氏宅跡」として国の史跡に指定され、平成25年8月、本堂が国宝となりました。
足利織姫神社
 1,300年の歴史と伝統を誇る機業地足利の守護神が奉られており、産業振興と縁結びの神様として広く親しまれています。
1,300年の歴史と伝統を誇る機業地足利の守護神が奉られており、産業振興と縁結びの神様として広く親しまれています。
明治12年に建てられましたが、翌年に火災により焼失。その後、昭和9年から3年の歳月をかけて再建し、当時では珍しい鉄筋コンクリートの社殿が完成しました。
朱塗りのお宮は緑に映えて景観が美しく、また、境内からは関東平野を一望できます。
栗田美術館
 伊萬里・柿右衛門・鍋島を所蔵する世界屈指の陶磁美術館です。
伊萬里・柿右衛門・鍋島を所蔵する世界屈指の陶磁美術館です。
足利市の郊外にあり、3万坪の豊かな自然に囲まれた広大な敷地には、格調高い建築物が点在し、世界の人々を魅了した名陶が常時展示されています。
足利の年中行事
節分鎧年越
 「鎧年越」は、約750年前の鎌倉時代中期、足利義兼の孫・泰氏(源姓足利氏4代目)が一族の結束と勢力を誇示する為、坂東武者500騎を鑁阿寺南大門に勢揃いさせたという故事にちなんだ古式ゆかしい行事です。
「鎧年越」は、約750年前の鎌倉時代中期、足利義兼の孫・泰氏(源姓足利氏4代目)が一族の結束と勢力を誇示する為、坂東武者500騎を鑁阿寺南大門に勢揃いさせたという故事にちなんだ古式ゆかしい行事です。
節分の夜、鎧・冑に身を固めた坂東武者が、法螺貝・陣太鼓を鳴らしながら、歴史絵巻さながらに市内を練り歩きます。
ふじのはな物語
 春の息吹を感じるこの時期、あしかがフラワーパークでは、350本以上の藤の花が咲き乱れます。世界一の美しさを誇る大藤は、まるで絵巻物の様。
春の息吹を感じるこの時期、あしかがフラワーパークでは、350本以上の藤の花が咲き乱れます。世界一の美しさを誇る大藤は、まるで絵巻物の様。
うすべに藤、むらさき藤、白藤、きばな藤といった色の移り変わりだけでなく、朝・昼・夜それぞれ違った花の表情もあしかがフラワーパークではお楽しみいただけます。
初山祭(ペタンコまつり)
 男浅間(上の宮)と女浅間(下の宮)で毎年山開きの6月1日に行われます。
男浅間(上の宮)と女浅間(下の宮)で毎年山開きの6月1日に行われます。
このお祭りは400年以上も前から始められたといわれ、この1年の間に生まれた赤ちゃんの額に御朱印を押してもらい、無病・息災・開運を祈願します。
神前で赤ちゃんの額に神社の御朱印を押すことから「ペタンコまつり」の名で親しまれています。
足利花火大会
 足利夏まつりのクライマックスを飾る「足利花火大会」は明治36年から始まった伝統ある大会です。関東有数の規模を誇り、関東一円から多くの観覧者で賑わうため、「50万人の夕涼み」と呼ばれています。
足利夏まつりのクライマックスを飾る「足利花火大会」は明治36年から始まった伝統ある大会です。関東有数の規模を誇り、関東一円から多くの観覧者で賑わうため、「50万人の夕涼み」と呼ばれています。
恒例の尺玉、仕掛け花火、大ナイアガラやスターマインなど約2万発以上が打ち上げられます。
足利灯り物語
 足利の街に点在する歴史的な文化遺産を、足利銘仙柄の特製行灯「銘仙灯り」と花手水などを設置し、幻想的な雰囲気を演出します。
足利の街に点在する歴史的な文化遺産を、足利銘仙柄の特製行灯「銘仙灯り」と花手水などを設置し、幻想的な雰囲気を演出します。
この秋にしか出会えない、期間限定の灯りのイベント。はっと息を呑み、思わずカメラを手に取る美しい光景をぜひお楽しみください。
光の花の庭 Flower Fantasy
 日本夜景遺産「日本三大イルミネーション」に認定され、イルミネーションアワードで7年連続日本一となったあしかがフラワーパーク。園全体を約500万球のLEDで彩り、冬の木々に美しい光の花が咲き誇ります。花のプロが創り出す、花と光の芸術作品をお楽しみください。
日本夜景遺産「日本三大イルミネーション」に認定され、イルミネーションアワードで7年連続日本一となったあしかがフラワーパーク。園全体を約500万球のLEDで彩り、冬の木々に美しい光の花が咲き誇ります。花のプロが創り出す、花と光の芸術作品をお楽しみください。
収穫祭
 晩秋の空の下、葡萄畑で音楽を聴きながらワインを楽しむ収穫祭は、毎年沢山の人で賑わいます。
晩秋の空の下、葡萄畑で音楽を聴きながらワインを楽しむ収穫祭は、毎年沢山の人で賑わいます。
その期間にしか飲めないできたてのワインをはじめ、ココ・ファームの各種ワインが勢揃い。開放的な葡萄畑で味わう格別な一杯をご堪能ください。
足利の工芸品
足利の味・ぐるめ
- 交通
- 電車でのアクセス
JR両毛線足利駅および東武伊勢崎線足利市駅下車
車でのアクセス
北関東自動車道足利ICおよび東北自動車道佐野藤岡IC
- 問い合わせ
- 一般社団法人足利市観光協会
- TEL:0284-43-3000 / FAX:0284-43-3333
- URL: https://www.ashikaga-kankou.jp/